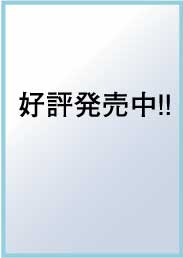キーワード:
分子配向技術と光・電子物性/液晶/有機太陽電池/有機トランジスタ/有機強誘電性メモリー/有機ラマンレーザー/発光性有機半導体/コレステリック液晶レーザー/バイオフォトセンサー/ナノスケールでの分子配向
刊行にあたって
最近,有機バイスへの関心が高まりつつある。有機デバイスの特長には,大面積・フレキシブルデバイスを構築できること,製作プロセスに印刷法を用いることができることなどが挙げられ,安価な機能デバイス構築が可能となる。一方,有機デバイスのさらなる高機能化には分子配向技術の活用が重要となる。
本書では,第1章で有機分子配向について概観した後,第2章で,さまざまな分子配向技術,また,それらを用いて作製した有機配向膜の光物性,電子物性について解説し,それぞれの有機分子配向技術の得失を明らかにする。液晶材料が良好な電荷伝導特性,発光特性を示すことが知られている。第3章では,これらの液晶のあたらしい配向技術,デバイス応用,全く新しい展開として液晶を溶媒として用いた有機単結晶作製などを述べる。第4章では,色素増感太陽電池,有機太陽電池における分子配向,第5章では,有機トランジスタと分子配向,第6章では,分子配向技術を用いた新規有機デバイスについて述べる。上述のとおり有機デバイスには大面積,フレキシブル,安価なる特長があるが,一方で,有機分子一分子でデバイスを構築できる究極の機能性材料である。高速化,高密度化が進み,シリコン集積回路が集積限界を迎えようとしている中,有機単分子デバイスの構築は極めて重要な課題である。最終章である第7章では,分子デバイス用有機分子合成,分子配線,ナノ電極,分子デバイスについて述べる。
内藤裕義(大阪府立大学)
「はじめに」より抜粋
著者一覧
八瀬清志 (独)産業技術総合研究所 久保野敦史 静岡大学 星野聡孝 大阪府立大学 上田裕清 神戸大学 三崎雅裕 (独)産業技術総合研究所 石川 謙 東京工業大学 奥居徳昌 東京工業大学 吉本則之 岩手大学 小林隆史 大阪府立大学 内藤裕義 大阪府立大学 舟橋正浩 (独)産業技術総合研究所 (現)東京大学 物部浩達 (独)産業技術総合研究所 清水 洋 (独)産業技術総合研究所 藤掛英夫 NHK放送技術研究所 鈴木成嘉 メルク㈱ 半那純一 東京工業大学 吉本尚起 ㈱日立製作所 内田 聡 東京大学 瀬川浩司 東京大学 宮坂 力 桐蔭横浜大学 池上和志 桐蔭横浜 池田信之 桐蔭横浜 藤井彰彦 大阪大学 當摩哲也 (独)産業技術総合研究所 阪井 淳 松下電工㈱ | 山成敏広 (独)産業技術総合研究所 斉藤和裕 (独)産業技術総合研究所 瀧宮和男 広島大学 西沢秀之 ㈱東芝研究開発センター 近松真之 (独)産業技術総合研究所 島田敏宏 東京大学 工藤一浩 千葉大学 森 朋彦 ㈱豊田中央研究所 菊澤良弘 ㈱豊田中央研究所 竹内久人 ㈱豊田中央研究所 南方 尚 旭化成㈱ 石田謙司 神戸大学 桑島修一郎 京都大学 山田啓文 京都大学 松重和美 京都大学 柳 久雄 奈良先端科学技術大学院大学 堀田 収 京都工芸繊維大学 小林俊介 (独)産業技術総合研究所 柄澤潤一 セイコーエプソン㈱ 尾崎雅則 大阪大学 内生蔵広幸 九州大学 八尋正幸 九州大学 安達千波矢 九州大学 皆方 誠 静岡大学 大坪徹夫 広島大学 |
目次 + クリックで目次を表示
1 はじめに
2 分子の間に働く力
3 真空中で分子を飛ばす
4 基板上での分子の振る舞い
5 エピタキシャル成長
6 直線分子の凝集機構
7 平面分子の凝集機構
8 球状分子の凝集機構
9 おわりに
第2章 分子配向技術と光・電子物性
1 有機蒸着薄膜の形成・配向機構
1.1 はじめに
1.2 配向機構
1.2.1 配向機構モデル
1.2.2 歳差運動モデル
1.2.3 熱力学的取り扱い
1.2.4 速度論的取り扱い
1.3 薄膜形成過程のin-situ観察
1.4 まとめ
2 有機薄膜のエピタキシャル方位とその予測
2.1 はじめに
2.2 有機エピタキシーにおける格子整合
2.3 point-on-line整合に基づく配向予測
2.4 分子方位とひずみの影響
2.5 おわりに
3 摩擦転写法による有機・高分子の分子配列制御
3.1 はじめに
3.2 PTFE摩擦転写膜の作製とその構造
3.3 PTFE摩擦転写膜上の有機分子の構造と機能
3.4 共役系高分子の摩擦転写膜の作製とその構造
3.5 おわりに
4 ラビングによる配向制御
4.1 はじめに
4.2 有機半導体の配向処理手法
4.3 ラビング手法による分子配向制御
4.3.1 液晶におけるラビング
4.3.2 低分子蒸着膜に対するラビング
4.4 配向薄膜の応用例
4.4.1 吸収型偏光板
4.4.2 回折型偏光板
4.4.3 配向薄膜の有機FETへの応用
5 真空蒸着重合法による分子配列制御された高分子薄膜の作製と電気的性質
5.1 はじめに
5.2 交互蒸着重合におけるモノマー分子鎖の基板上における吸着特性
5.3 薄膜の分子配列と分子量
5.4 薄膜の構造
5.5 4元系ナイロンの蒸着重合
5.6 その他の蒸着重合薄膜
5.7 交互蒸着重合薄膜の電気的性質
6 X線回折法による有機薄膜の配向評価
6.1 はじめに
6.2 膜の厚み方向の配向評価
6.3 面内の配向評価
6.4 まとめ
7 配向した有機高分子の光物性
第3章 液晶と分子配向
1 棒状分子が形成する液晶相での電子伝導—電荷輸送特性と液晶相の構造
1.1 はじめに
1.2 初期の研究と問題点
1.3 液晶相での電気伝導—イオン伝導と電子伝導
1.4 液晶相の構造とキャリア移動度の相関
1.5 液晶相温度領域の拡大と低温化
1.6 スピンコート法による液晶性薄膜の作製と薄膜トランジスターへの応用
1.7 ネマティック相やコレステリック相で本当に電子伝導は不可能か
2 直線偏光・円偏光赤外レーザー照射によるディスコティック液晶の配向制御
2.1 はじめに
2.2 赤外レーザー照射によるディスコティック液晶の配向制御
2.2.1 直線偏光赤外レーザーによるディスコティック液晶のカラムナー相における配向制御
2.2.2 円偏光赤外レーザー照射によるディスコティック液晶のカラムナー相における配向制御
2.2.3 自由電子レーザー以外の波長可変赤外レーザー光源
2.3 おわりに
3 液晶溶媒中でのペンタセン有機半導体の単結晶形成
3.1 ペンタセンの単結晶化に向けて
3.2 ペンタセンの蒸着膜
3.3 液晶溶媒を用いた溶液成長
3.3.1 ペンタセンの溶解
3.3.2 溶液セルを用いた析出過程
3.4 ペンタセン単結晶の構造観察
3.5 単結晶の析出制御
3.5.1 核発生の制御
3.5.2 成長核の配向制御
3.5.3 成長過程の制御
3.6 単結晶の異方性
3.6.1 吸収2色性
3.6.2 ラマン散乱光の異方性
3.7 今後の課題
4 発光性液晶の研究動向
4.1 はじめに
4.2 発光機構
4.2.1 電荷注入機構
4.2.2 電荷移動機構
4.2.3 電荷再結合,発光過程
4.3 研究動向
4.3.1 低分子液晶
4.3.2 液晶性高分子あるいはオリゴマー
4.3.3 感光性液晶
4.4 おわりに
5 液晶物質における電気伝導
5.1 はじめに
5.2 液晶物質における電子伝導の発見
5.3 代表的な電子伝導性液晶物質
5.4 電荷輸送特性の特質
5.4.1 液晶分子の凝集構造と伝導
5.4.2 分子配向と伝導特性
5.4.3 両極性伝導
5.4.4 伝導の特質と伝導機構
5.4.5 分子配向に基づく構造欠陥
5.4.6 移動度から見た液晶物質の位置づけ
第4章 有機太陽電池と分子配向
1 有機太陽電池の現状と課題
1.1 はじめに
1.2 色素増感太陽電池
1.2.1 色素増感太陽電池の基本構成
1.2.2 色素増感太陽電池の発電原理
1.2.3 太陽電池の性能評価
1.2.4 高効率化へ向けた要素技術
1.2.5 長寿命化への課題
1.2.6 製品化へ向けた大型化の課題
1.3 おわりに
2 色素増感型太陽電池の最新動向
2.1 はじめに
2.2 高比表面積酸化チタンの開発
2.3 高効率色素の開発
2.4 透明電解質溶液の開発
2.5 おわりに
3 色素増感太陽電池のプラスチック化とカーボン材料による全固体化
3.1 はじめに
3.2 色素増感太陽電池のプラスチック化
3.3 カーボン材料を用いる電池の固体化
3.4 フルプラスチックの固体色素増感太陽電池
3.5 大面積プラスチックDSCモジュール
4 ドナー/アクセプタ相互浸透界面の作製と有機薄膜太陽電池
4.1 はじめに
4.2 C60/導電性高分子相互浸透界面の作製及びその特性
4.3 ITO表面の微細加工効果
4.4 共蒸着層挿入効果
4.5 ZnO層挿入効果
4.6 おわりに
5 共蒸着で作るバルクヘテロ接合と高効率有機太陽電池
5.1 はじめに
5.2 バルクヘテロ接合の形成手法
5.3 バルクヘテロ接合の効果
5.4 低分子半導体を用いたバルクヘテロ接合
5.5 ポリマーを用いたバルクヘテロ接合
5.6 有機薄膜太陽電池の高効率化に必要な技術
5.7 バルクヘテロ接合の進化
5.8 今後の展開
第5章 有機トランジスタと分子配向
1 新しい有機トランジスタ材料の設計と合成
1.1 はじめに
1.2 既存材料
1.3 新規材料の検討
1.3.1 ナフトジチオフェン(NDT)系
1.3.2 オリゴセレノフェン系
1.4 新規材料の展開
1.4.1 ベンゾジカルコゲノフェン(BDX)系材料
1.4.2 ベンゾカルコゲノフェノベンゾカルコゲノフェン(BXBX)系材料
1.4.3 硫黄体への回帰・ジフェニルーベンゾチエノベンゾチオフェン(DPh-BTBT)
1.5 おわりに
2 有機トランジスタにおける電荷輸送機構とディスオーダーの影響
2.1 はじめに
2.2 分子性結晶と輸送の基礎のまとめ
2.2.1 分子性結晶とポーラロン準位
2.2.2 分子性結晶の状態密度拡がり
2.2.3 キャリアの平均自由行程
2.2.4 電子交換レート(ホッピングレート)
2.3 有機電界効果型トランジスタ
2.3.1 ホッピング移動度を考慮したグラジュアルチャネル近似モデル
2.3.2 電流-電圧特性の再現
2.4 ディスオーダーの影響
2.4.1 測定されたトラップ準位もしくは状態密度の拡がり幅
2.4.2 理論から示唆されること
2.5 まとめ
3 可溶性フラーレン誘導体のトランジスタと分子配向
3.1 はじめに
3.2 可溶性フラーレン誘導体TFT
3.3 長鎖アルキル基を有するC60誘導体
3.4 アルキル鎖の付加位置依存性
3.5 おわりに
4 有機FET中の電荷の正体:分子積層・配向制御による伝導機構の研究
4.1 はじめに
4.2 有機半導体の伝導機構に関する研究例とこれまでの知見
4.3 バンド構造の決定のためのナノ周期構造基板を用いたペンタセン分子配向制御
4.4 FET構造による電流誘起光重合
4.5 まとめ
5 縦型有機トランジスタと光電子デバイス応用
5.1 はじめに
5.2 縦型有機トランジスタ
5.3 有機発光トランジスタ
5.4 おわりに
6 ヘキサベンゾコロネン有機トランジスタと層状分子配向
6.1 はじめに
6.2 ヘキサベンゾコロネン誘導体
6.3 トランジスタ特性
6.4 分子配向解析
6.4.1 分子配向測定方法
6.4.2 分子配向測定結果
6.5 まとめ
7 縮合多環芳香族化合物の自己組織化と溶液プロセス薄膜トランジスタへの展開
7.1 はじめに
7.2 縮合多環芳香族化合物の自己組織化
7.3 ペンタセンの溶液プロセスへの展開
7.4 塗布ペンタセン薄膜のトランジスタ特性
第6章 新規有機デバイスと分子配向
1 有機強誘電性メモリー
1.1 はじめに
1.2 有機メモリー
1.3 強誘電性メモリーの原理
1.4 有機強誘電体を用いた不揮発メモリー
1.4.1 有機強誘電体
1.4.2 有機強誘電体薄膜の構造・分子配向
1.4.3 VDFオリゴマーの強誘電特性,誘電特性
1.4.4 疲労特性,周波数依存性
1.4.5 ナノスケール分極反転操作
1.5 おわりに
2 有機ラマンレーザー
2.1 はじめに
2.2 TPCO低次元結晶の作製
2.3 TPCO低次元結晶のASEおよびSRRS特性
2.4 SRRSの発生機構
2.5 おわりに
3 強誘電体高分子を用いた有機トランジスタメモリ
3.1 はじめに
3.2 SiをペースとするリジッドFeRAM
3.3 1T型FeRAMと全有機材料によるフレキシブルFeRAM
3.4 有機強誘電体P(VDF/TrFE)
3.5 P(VDF/TrFE)薄膜の結晶化および配向性
3.6 有機強誘電体P(VDF/TrFE)と有機半導体F8T2を用いたフレキシブル1T型有機FeRAM
3.7 有機FeRAMの課題
4 欠陥を導入したコレステリック液晶レーザー
4.1 はじめに
4.2 螺旋周期構造とフォトニック結晶
4.3 液晶レーザー
4.4 螺旋周期の欠陥と光局在
4.5 螺旋欠陥と高いQ値を有する欠陥モード
4.6 おわりに
5 ピレン誘導体を用いた有機発光型トランジスタ材料の開発と高効率化
5.1 はじめに
5.2 発光性有機半導体の材料設計
5.3 テトラフェニルピレンの光学特性とトランジスタ特性
5.4 4置換ピレン誘導体を用いたOLEFETのデバイス特性
5.5 2置換体ピレン誘導体を用いたOLEFETのデバイス特性
5.6 ドーピングによる高性能化
5.7 おわりに
6 光合成タンパク質を用いたバイオフォトセンサー
6.1 はじめに
6.2 FETによる光電流の検出
6.3 PSI修飾FETを用いた画像入力
6.4 再構成PSI修飾FETの光応答
6.5 おわりに
第7章 ナノスケールでの分子配向
1 ナノデバイス用有機分子の合成
1.1 はじめに
1.2 オリゴチオフェンの合成
1.3 電界効果トランジスター材料の開発
1.4 電界発光材料の開発
1.5 光電変換材料の開発
1.6 分子ワイヤーの開発
1.7 まとめ
2 イミダゾリルポルフィリンのナノ自己組織配位体
2.1 はじめに
2.2 配向制御された自己組織化
2.3 鎖状ポルフィリンナノ連鎖体
2.4 リング状ポルフィリンナノ組織体
2.5 おわりに
3 錯体の分子配向制御による表面積層化とその機能
3.1 はじめに
3.2 基板表面上への分子の配向を制御した固定化
3.3 多脚型アンカー基をもつ分子
3.4 基板表面での分子ユニットの積層化
3.5 表面自己組織化単層および積層膜の機能
3.6 トップダウン法とボトムアップ法との融合による配線技術
3.7 おわりに
4 分子配向技術の将来に向けて
4.1 はじめに
4.2 分子系への情報の注入
4.2.1 分子構造自体が情報をもって組織化する
4.2.2 テンプレートから情報を与える
4.2.3 基板から情報を与える
4.2.4 界面による制御で情報を与える
4.2.5 外場により情報を与える
4.2.6 走査プローブ顕微鏡の手法で情報を与える
4.2.7 ナノリソグラフィーにより情報を与える
4.3 おわりに
5 分子被覆導線の電子機能と集積化
5.1 はじめに
5.2 分子被覆導線
5.3 分子被覆導線の作製
5.4 分子被覆導線の導電率測定
5.5 分子被覆導線の集積化
5.6 おわりに
6 ナノギャップ電極と単一分子の電気伝導特性
6.1 はじめに
6.2 ナノギャップ電極の作製方法
6.2.1 Break junctionによる方法
6.2.2 Shadow evaporationを用いた方法
6.2.3 Metal depositionによる方法
6.2.4 金ナノ微粒子を用いた方法
6.2.5 集束イオンビームを用いた方法
6.3 単一分子の電気伝導特性
6.4 まとめ
この商品を買った人はこちらの商品も購入しています。
インクジェット技術入門〜基礎から応用まで幅広く解説〜
価格(税込): 41,800 円
透明導電膜の新展開 IV《普及版》
価格(税込): 7,480 円
エレクトロクロミックデバイスの開発最前線
価格(税込): 71,500 円
食品造粒技術ハンドブック
価格(税込): 8,800 円
機能性ポリウレタンの開発と応用
価格(税込): 63,800 円
高分子材料の分解制御技術
価格(税込): 64,900 円