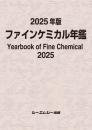キーワード:
希土類/資源/精錬/リサイクル/希土類鉱石/希土類金属/希土類合金/希土類酸化物/磁石/光機能分野/蛍光体/EL/レーザ/ファイバ/エレクトロニクス機能/電子セラミックス/熱電変換材料/エネルギー機能/触媒/ペロブスカイト/排ガス/浄化
刊行にあたって
長く続いた経済の不況にもようやく明るい見通しが語られ始めた。ものづくりへの意欲が回復してきたのはまことに喜ばしい兆候である。しかしこの回復とは,かつての「安物」を大量に製造していた時代への回帰ではない。機能の追及と環境への配慮を両立させた「ものづくりの新しいパラダイム」の構築が求められ,現に築かれつつあるといってよい。このような状況下での材料開発の共通の目標は「少量と高機能」であろう。「ナノサイエンス」,「ナノテクノロジー」が声高に叫ばれているゆえんはここにある。
20世紀は「エレクトロニクス時代」の幕開けとその成長を短期間に成し遂げた偉大な時代であった。この偉大さはまだまだ続く。21世紀は,エレクトロニクスに加え,「光-フォトニクス」と「バイオサイエンス」が材料開発の主戦場となるはずである。そして「希土類」はこれらの三分野,とりわけエレクトロニクスとフォトニクスにおいて主役の一員であることはよく知られている。本書は,これら三分野における「希土類」の材料への展開のうち,最近の動きを中心にまとめたものである。
学問体系をいつも「基礎」と「応用」に分けてしまうのは問題がないわけではないが,読者の便宜を優先するとすれば,このように分類して,欲しい情報への到達を容易にするというのも一方法である。基礎に関しては,数年前に㈱化学同人より『希土類の科学』が刊行されているのでこれにゆだね,本書はそのスコープを「応用」に集中した。
本書は原料から材料まで,その材料も磁性材料,発光材料から,有機合成の触媒,バイオテクノロジーまで,今注目されているトピックスをすべて,網羅している。想定している読者層は忙しい専門家であって,いわゆる初心者ではない。多忙な開発技術者に代わって,最近の情報を読んで解説している。
(「刊行に際して」より)
2005年11月 足立吟也
著者一覧
吉田紀史 信越化学工業㈱ 石垣尚幸 ㈱NEOMAX 太田晶康 ㈱NEOMAX 須田栄作 阿南化成㈱ 東馬秀夫 ㈱三徳 兜森俊樹 ㈱日本製鋼所 山本和彦 ㈱三徳 小見山昌三 三菱マテリアル㈱ 徳永雅亮 日立金属㈱ 大森賢次 住友金属鉱山㈱ 深道和明 東北大学 杉本 諭 東北大学 下村康夫 ㈱三菱化学科学技術研究センター 清水義則 日亜化学工業㈱ 村﨑嘉典 日亜化学工業㈱ 三上明義 金沢工業大学 坂野 晋 日立ライティング㈱ 太田雅壽 新潟大学 長谷川靖哉 奈良先端科学技術大学院大学 田部勢津久 京都大学 白井一志 ㈱グラノプト 村上雅人 芝浦工業大学 宍戸統悦 東北大学 岡田 繁 国士舘大学 和田信之 ㈱村田製作所 白露幸祐 ㈱村田製作所 新見秀明 ㈱村田製作所 田村真治 大阪大学 | 北川二郎 広島大学 高畠敏郎 広島大学 境 哲男 (独)産業技術総合技術研究所;神戸大学 尾崎哲也 (独)産業技術総合技術研究所 武信弘一 三菱重工業㈱ 森 一剛 三菱重工業㈱ 寺岡靖剛 九州大学 田中裕久 ダイハツ工業㈱ 小川昭弥 大阪府立大学 野元昭宏 大阪府立大学 河里 健 セイミケミカル㈱ 増井敏行 大阪大学 横田和彦 Rhodia Aubervilliers Research and Technology Center Franck Fajardie Rhodia Aubervilliers Research and Technology Center Jean-Noel Berte Rhodia Electronics & Catalysis Electronics 松井光二 東ソー㈱ 窪田吉孝 東ソー・セラミックス㈱ 渡利広司 (独)産業技術総合研究所 中野裕美 龍谷大学 小林靖之 大阪市立工業研究所 前田昌子 昭和大学 矢部信良 ㈱コーセー 築部 浩 大阪市立大学 片岡悠美子 大阪市立大学 小宮山真 東京大学 草場光博 大阪産業大学 足立吟也 日本希土類学会;大阪大学;日本分析化学専門学校 |
目次 + クリックで目次を表示
1 希土類の資源
1.1 希土類鉱石の種類
1.2 希土類鉱石の歴史と現状
1.3 希土類鉱石の埋蔵量
2 分離・精製技術
2.1 はじめに
2.2 鉱石の選鉱と分解処理
2.3 分離精製
2.3.1 古典的方法
2.3.2 イオン交換法
2.3.3 溶媒抽出法
(1)原理
(2)抽出剤
(3)装置
2.4 純度
3 リサイクル技術
3.1 はじめに
3.2 ネオジム系焼結磁石の成分と資源
3.3 磁石スクラップの発生
3.4 固形状スクラップのリサイクル
3.5 粉末状スクラップのリサイクル
3.6 市場から回収した磁石スクラップのリサイクル
3.7 おわりに
第2章 希土類酸化物および希土類金属・合金の製造
1 希土類酸化物の調製と保管
1.1 はじめに
1.2 希土類酸化物の調製
1.3 保管
2 希土類金属の製造
2.1 はじめに
2.2 電解法
2.2.1 塩化物電解法
2.2.2 酸化物電解法
2.3 熱還元法
2.3.1 還元蒸留法
2.3.2 カルシウム還元法
2.4 おわりに
3 希土類合金の製造
3.1 水素吸蔵合金の製造
3.1.1 はじめに
3.1.2 水素吸蔵合金の製造プロセス
3.1.3 電池特性に与える合金の金属学的な特性と凝固プロセスへの要求
3.1.4 おわりに
3.2 希土類磁石合金の製造
3.2.1 溶解および鋳造
3.2.2 SmCo磁石合金の鋳造組織
3.2.3 NdFeB磁石合金の鋳造組織
3.2.4 まとめ
3.3 光磁気記録用スパッタリングターゲット
3.3.1 はじめに
3.3.2 アモルファス希土類-遷移金属合金膜
3.3.3 希土類-遷移金属合金ターゲット
3.3.4 今後の光磁気記録材料
第3章 磁気機能分野への応用
1 永久磁石-焼結磁石
1.1 はじめに
1.2 結晶構造と物性値
1.3 磁気特性と特長
1.4 製造方法
1.5 応用分野
1.6 おわりに
2 希土類ボンド磁石
2.1 はじめに
2.2 等方性磁石粉
2.2.1 NdFeB系磁石粉
2.2.2 ナノコンポジット磁石粉
2.2.3 SmFeN系磁石粉
2.2.4 成形方法
2.3 異方性磁石粉
2.3.1 NdFeB系磁石粉
2.3.2 SmFeN系磁石粉
2.3.3 成形方法
2.3.4 新成形方法
2.4 着磁特性
2.5 おわりに
3 磁歪材料
3.1 はじめに
3.2 Co系およびFe系希土類化合物の磁気的性質の特徴
3.3 Fe系化合物の磁歪特性の制御
3.4 磁歪の温度依存性
3.5 プレストレス
3.6 TbFe2系の最近の進展
3.7 新しいメカニズムによる巨大磁歪材料
3.7.1 双晶磁歪
3.7.2 メタ磁性転移による等方性磁歪
3.8 おわりに
4 磁気冷凍材料
4.1 はじめに
4.2 磁気冷凍の原理と特徴
4.3 遍歴電子メタ磁性体と磁気熱量効果
4.4 熱特性
4.5 低温領域への展開
4.6 おわりに
5 電磁波吸収体
5.1 はじめに
5.2 電磁波吸収体の評価と磁気共鳴
5.3 希土類-鉄-ボロン系化合物を利用した電磁波吸収体
5.3.1 希土類元素置換による異方性制御とGHz帯電磁波吸収特性
5.3.2 ナノコンポジット化による異方性制御とGHz帯電磁波吸収特性
5.4 希土類磁石化合物の不均化反応により生成する微細α-Feを利用した電磁波吸収体
5.5 おわりに
第4章 光機能分野への応用
1 カラーPDP用蛍光体
1.1 はじめに
1.2 カラーPDP用蛍光体に求められる特性と課題
1.3 蛍光体各論
1.3.1 青色蛍光体
1.3.2 緑色蛍光体
1.3.3 赤色蛍光体
1.4 最近のパネル改良動向と蛍光体
2 白色LED用蛍光体
2.1 はじめに
2.2 白色化の手法
2.2.1 グループA
2.2.2 グループB
2.2.3 グループC
2.3 効率の改善
2.4 演色性の改善
2.5 LED用蛍光体一覧
2.6 まとめ
3 液晶バックライト用蛍光体
3.1 はじめに
3.2 蛍光体に要求される特性と実用材料
3.3 改良技術
3.4 おわりに
4 希土類蛍光体-長残光蛍光体
4.1 はじめに
4.2 長残光蛍光体の種類と特性
4.2.1 長残光蛍光体の発光及び残光特性
4.2.2 長残光性蛍光体の耐久性
(1)耐熱性
(2)耐薬品性及び耐光性
4.3 応用
4.3.1 残光性蛍光ランプ
4.3.2 残光性タイル
4.3.3 パステルカラーの長残光蛍光体
4.4 その他の長残光蛍光体
4.5 おわりに
5 EL(エレクトロルミネッセンス)
5.1 はじめに
5.2 無機EL
5.2.1 Ce3+イオンを付活した無機EL材料
5.2.2 Eu2+イオンを付活した無機EL材料
5.2.3 Tb3+イオンを付活した無機EL材料
5.3 有機EL
5.3.1 発光効率とエネルギー移動過程
5.3.2 希土類元素を用いた有機EL素子
6 照明用蛍光体
6.1 はじめに
6.2 蛍光ランプ用蛍光体
6.2.1 蛍光ランプ
6.2.2 要求される特性
6.2.3 実用蛍光体
6.2.4 蛍光体の開発動向
6.2.5 周辺技術動向(保護膜)
6.2.6 量産技術動向
6.2.7 新しいタイプの光源として
6.2.8 計算化学の利用
6.2.9 演色性の検討
6.2.10 希土類の回収・再生
6.3 高輝度放電灯(HIDランプ)用蛍光体
6.3.1 蛍光水銀ランプ
6.3.2 要求される特性
6.3.3 実用蛍光体
6.4 無水銀蛍光ランプ用蛍光体
7 放射線シンチレータ用発光材料
7.1 はじめに
7.2 希土類酸化物単結晶
7.3 希土類フッ化物単結晶
8 希土類錯体を用いた発光材料
8.1 はじめに
8.2 希土類錯体を用いた発光機能材料
8.3 希土類錯体を用いた発光センサー材料
8.4 おわりに
9 希土類レーザ
9.1 YAGレーザ
9.1.1 はじめに
9.1.2 半導体レーザ励起が主流に!!
9.1.3 Yb:YAGレーザ
(1)Yb系固体レーザのエネルギー準位
(2)YbにとってYAGホストは?
9.1.4 透明多結晶YAGレーザ
9.2 希土類ガラスレーザ
9.2.1 はじめに
9.2.2 Ybファイバレーザ
10 希土類添加ファイバ
10.1 ファイバレーザの特徴
10.1.1 高冷却能力
10.1.2 低閾値,低損失,高破壊閾値
10.1.3 導波路特性
10.2 光ファイバ増幅器
10.3 アップコンバージョンファイバ
11 ファラディ回転子・光アイソレータ
第5章 エレクトロニクス機能分野への応用
1 超伝導材料
1.1 はじめに
1.2 希土類元素を含む高温超伝導材料
1.2.1 La2-xBaxCuO4系超伝導材料
1.2.2 REBa2Cu3Oy系超伝導材料
1.3 希土類系超伝導材料の応用
1.3.1 高温超伝導線材
1.3.2 超伝導バルク材
1.3.3 薄膜応用
1.4 おわりに
2 電子放射材料
3 電子セラミックス
3.1 コンデンサ用希土類添加誘電体材料
3.1.1 セラミックコンデンサの概説
3.1.2 温度補償用セラミックコンデンサ材料における希土類元素について
3.1.3 高誘電率セラミックコンデンサ材料における希土類元素について
(1)高誘電率セラミックコンデンサ材料の問題点
(2)高誘電率セラミックコンデンサ材料における希土類元素添加効果
3.2 圧電素子用希土類添加誘電体材料
3.3 サーミスタ用途での希土類の役割
3.3.1 はじめに
3.3.2 PTCサーミスタ
(1)特徴と原理
(2)応用
3.3.3 NTCサーミスタ
(1)特徴
(2)応用
3.3.4 サーミスタにおける希土類イオンの役割
(1)PTCサーミスタにおける希土類の役割
(2)新サーミスタ材料における希土類の役割
3.4 化学センサ
3.4.1 はじめに
3.4.2 ガスセンサ
(1)半導体型
(2)固体電解質型
3.4.3 イオン電極
4 熱電変換材料
4.1 最近の展開
4.2 希土類近藤半導体
4.3 希土類充填スクッテルダイト
4.4 その他の物質
4.5 課題
第6章 エネルギー機能分野への応用
1 水素吸蔵合金
1.1 二次電池用合金
1.1.1 はじめに
1.1.2 ニッケル水素電池と合金開発
1.1.3 高容量合金の開発と実用化
1.1.4 おわりに
1.2 電気自動車用合金
1.2.1 はじめに
1.2.2 電気自動車
1.2.3 ハイブリッド電気自動車
(1)ハイブリッド電気自動車の高性能化
(2)HEV用ニッケル水素電池の高性能化
(3)新型HEV用ニッケル水素電池の開発
1.2.4 燃料電池電気自動車
1.2.5 おわりに
2 燃料電池用固体電解質
2.1 固体酸化物形燃料電池
2.2 固体電解質材料
2.3 ジルコニア
2.4 中温作動
3 電極材料
3.1 空気極材料
3.2 燃料極材料
第7章 触媒への応用
1 希土類複合金属酸化物触媒
1.1 はじめに
1.2 ペロブスカイト触媒研究の最近の動向
1.3 自動車用三元触媒としてのペロブスカイト
1.4 酸化触媒としてのペロブスカイト
1.5 リフォーミング用担持金属触媒前駆体としてのペロブスカイト
1.6 電気化学デバイス用触媒
1.7 酸素分離およびメンブレンリアクターへの展開
1.8 おわりに
2 自動車排ガス浄化触媒
2.1 はじめに
2.2 自動車触媒と希土類元素
2.3 酸素吸蔵能力
2.3.1 セリアの酸素吸蔵能力
2.3.2 セリアの耐熱性と酸素吸蔵レスポンス向上
2.4 インテリジェント触媒
2.4.1 不老不死の自動車触媒
2.4.2 自己再生機能の解明
2.5 おわりに
3 希土類合成触媒
3.1 はじめに
3.2 有機合成おける希土類試薬の特性
3.3 4価希土類合成試薬による酸化反応
3.4 3価希土類合成試薬の利用
3.4.1 スカンジウムトリフラート
3.4.2 有機セリウム求核試薬(Imamoto reagent)
3.4.3 希土類不斉触媒
3.5 2価希土類合成試薬を用いる還元的分子変換反応
4 高分子重合触媒
第8章 研磨剤・釉薬・顔料への応用
1 研磨剤(CMP用研磨剤)
1.1 ガラス表面研磨
1.2 半導体シリコンウェハー表面仕上げ研磨剤
2 セラミックス用釉薬および顔料への応用
2.1 実用顔料
2.2 最近の研究開発動向
2.2.1 複合酸化物系
2.2.2 希土類リン酸塩系
2.2.3 モリブデン酸塩およびタングステン酸塩系
2.2.4 ペロブスカイト型酸化物系
2.2.5 酸窒化物系
3 プラスチック顔料への応用
3.1 はじめに
3.2 希土類硫化物の構造と色・製造プロセス
3.3 プラスチック顔料としての性能と展望
3.4 希土類硫化物顔料の人体・環境への影響
3.5 おわりに
第9章 構造材料への応用
1 ジルコニア・セラミックス
1.1 はじめに
1.2 ジルコニアの種類と特徴
1.3 Y-TZP及びジルコニア・セラミックスの用途
1.4 Y-TZP用原料粉末の製造方法
1.5 Y-TZP微粉末の微構造と組成
2 エンジニアリングセラミックスと希土類助剤
2.1 はじめに
2.2 エンジニアリングセラミックスの特徴及び特性
2.3 機能発現における焼結助剤の役割
2.3.1 強度
2.3.2 破壊靱性
2.3.3 熱伝導率
2.4 おわりに
3 耐食性・耐酸化性コーティング
3.1 はじめに
3.2 希土類元素と腐食抑制
3.3 セリウム化成処理
3.4 耐酸化性コーティング
第10章 医療・生理学・紫外線防御分野への応用
1 診断試薬,検査薬
1.1 はじめに
1.2 時間分解蛍光イムノアッセイによるベロ毒素蛋白の測定
1.3 時間分解蛍光イムノアッセイによるVT遺伝子のPCR増幅産物の測定
1.4 時間分解蛍光イムノアッセイによるビタミンD受容体遺伝子多型の解析
2 紫外線吸収材料としての応用
2.1 紫外線カットガラス
2.2 紫外線カットフィルムおよび繊維
2.3 最近の研究開発動向
3 化粧品への応用
3.1 なぜセリアか
3.2 ソフト溶液法によるナノサイズセリアの合成
3.3 酸化触媒活性の評価
3.4 光触媒活性の評価
3.5 光学的特性の評価
3.5.1 粒子の色調
3.6 まとめ
第11章 希土類の応用の将来展望
1 希土類錯体を用いる分子認識と発光センシング
1.1 希土類錯体の特徴
1.2 希土類錯体による分子認識
1.3 希土類錯体による発光センシング
1.4 今後の展望
2 人工制限酵素による巨大DNAの切断と遺伝子操作
2.1 はじめに
2.2 Ce(IV)イオンによるDNAの切断
2.3 人工制限酵素の設計
2.3.1 戦略
2.3.2 触媒とホット・スポットの開発
2.4 人工制限酵素によるDNA切断と遺伝子操作
2.4.1 2重らせんDNA中の所定のリン酸ジエステル結合の活性化(ホット・スポットの形成
2.4.2 DNAの位置選択的切断
2.4.3 人工制限酵素を用いた遺伝子組み換え
2.5 おわりに
3 希土類内包フラーレン・カーボンナノチューブ
3.1 金属内包フラーレン・カーボンナノチューブとは
3.2 希土類内包フラーレン・カーボンナノチューブの合成およびその応用
3.2.1 金属内包フラーレン
3.2.2 金属内包カーボンナノチューブ
第12章 最近の材料研究における希土類の位置づけ
1 はじめに
2 Chemical Abstractsから見た材料研究の動向
3 希土類研究における新しい潮流
〈続〉次世代蛍光体材料の開発
価格(税込): 71,500 円
レアアースの最新技術動向と資源戦略《普及版》
価格(税込): 4,730 円
次世代蛍光体材料の開発《普及版》
価格(税込): 4,400 円
海底鉱物資源の産業利用《普及版》
価格(税込): 4,730 円
2025年版ファインケミカル年鑑
価格(税込): 92,400 円